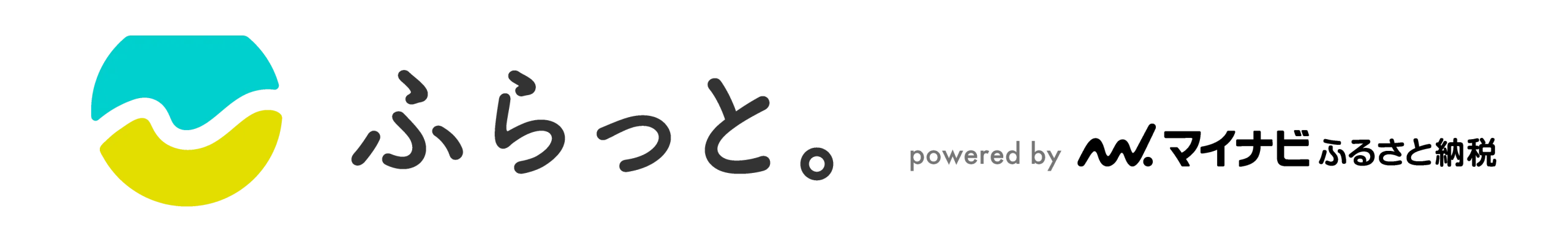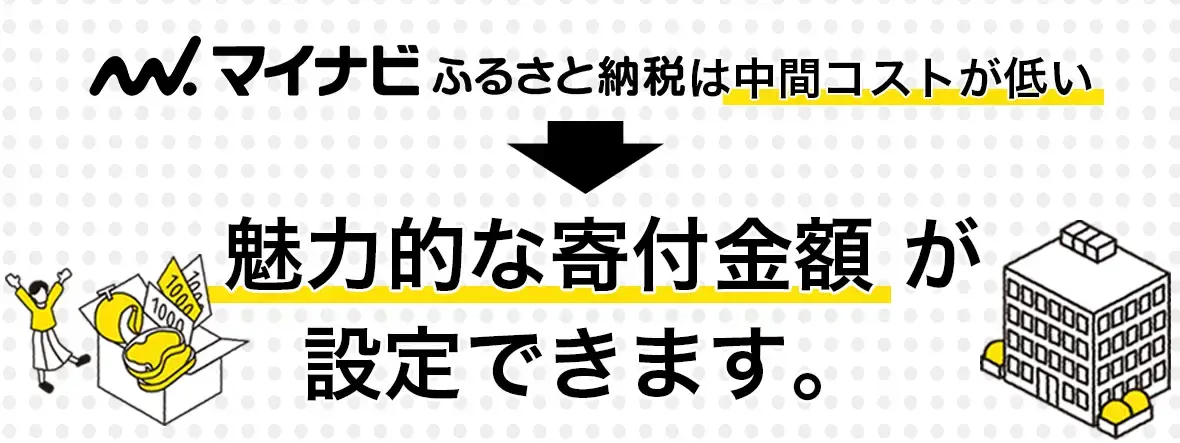これからふるさと納税を始めようと考えている会社員の方。
会社員でもふるさと納税できるのか、やり方はどうしたらいいのか、わからなくてなかなか始められないという方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税には職業や業種の制限はありません。
もちろん、会社員でもふるさと納税を利用することができます。
むしろ、会社員こそふるさと納税をすべきなんです!
今回の記事では、会社員がふるさと納税をするメリットや、ふるさと納税のやり方を詳しく解説します。
ふるさと納税で人気の返礼品の紹介もありますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください!
ふるさと納税の基礎知識
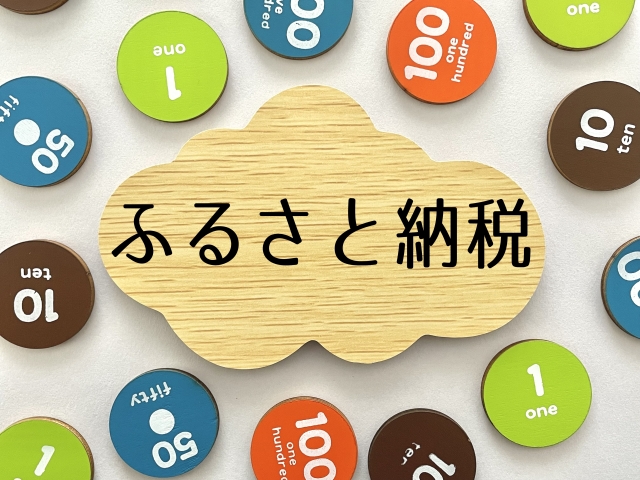
それでは、まずはふるさと納税の基礎知識からおさらいしていきましょう。
詳細な説明となると制度の話や難しい計算が出てきてしまいますが、そうなるとちょっと足を踏み入れにくいですよね。
ここでは難しい話を抜きにして、ふるさと納税の概要を分かりやすく簡単に説明していきます!
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、日本各地の自治体に寄附することで税額控除を受けたり、自治体から寄附のお礼として返礼品をもらうことができる制度のこと。
マイナビふるさと納税など、ふるさと納税のポータルサイトから手軽に申し込むことが可能です。
応援したい町や興味のある事業など、自分で自治体を選んで寄附をすることができ、その寄附金の使い道も指定できます。
また、もらえる返礼品は日本各地の名産や特産品、家電や旅行券など様々なジャンルの取り扱いがあり、返礼品から寄付先を選ぶことも可能です。
ただし、自分の住民票が登録されている自治体へのふるさと納税では、返礼品を受け取ることができませんので注意しましょう。
税額控除って何?
ふるさと納税をすると、寄附額の分だけ翌年の所得税や住民税から控除(税金から差し引かれる)を受けることができます。
寄附に対する控除の制度は他にもありますが、ふるさと納税は寄附の全額が控除の対象になるという特別なもの。
ふるさと納税をすることによって、翌年の税金を前払いするというイメージです。
ただし、控除される額には上限があり、収入や家族構成によって人それぞれ異なります。
上限までの寄附であれば、寄附額から自己負担2,000円を引いた全額が税金から差し引かれる形で戻ってくるというわけです。
もうひとつ。
ふるさと納税の寄附の上限はありませんので、いくらでも寄附することができます。
ですが、控除の上限を超えてふるさと納税した場合、超えた分は全て自己負担に加算されますので注意しましょう。
ふるさと納税の何がお得なの?
税額控除を受けられるのもふるさと納税の特徴ですが、それはあくまで税金の前払い。
ふるさと納税がお得といわれる最大のポイントは、自治体からのお礼としてもらえる「返礼品」です。
返礼品は自治体が寄附のお礼として、寄附額に応じた品物を用意しています。
その返礼品の調達費用は、寄附額の30%までと決められています。
・10,000円の寄附に対する返礼品は、3,000円程で調達できる品物
・50,000円の寄附に対する返礼品は、15,000円程で調達できる品物
前項で解説のとおり、控除の上限までは自己負担2,000円で寄附できます。
控除上限50,000円の方が上限いっぱいまでふるさと納税すると、2,000円の支払いで15,000円相当の品物を手に入れることができるということに。
さらに、自己負担を除いた48,000円は翌年の税金から差し引かれます。
このように、実質2,000円を支払うだけで翌年の税金を前払いでき、さらに2,000円の支払いよりも高価な返礼品を受け取れるという、かなりお得なしくみになっているのです。
いつまでにふるさと納税すれば良い?
ふるさと納税の寄附の申し込み自体は、各ポータルサイトから365日24時間いつでも申し込み可能です。
ただし、翌年の税額控除が関係するため、毎年1月1日から12月31日までの1年間で処理が区切られています。
12月31日の23時59分までに手続きが完了しているものについては、その年のふるさと納税ということになり翌年の控除対象となります。
ここで注意が必要なのが「手続きの完了 = 寄附金の支払いまで完了」という点。
クレジットカードやオンライン決済であれば決済の完了日、銀行振り込みであれば指定口座に振り込んだ日、ということになります。
カレンダーによっては年末ギリギリだと支払いが完了できない場合もありますので、その年のふるさと納税として処理したいのであれば余裕を持って申し込みましょう。
もし手続きが翌年に繰り越してしまった場合は、翌年分のふるさと納税としてカウントされ、無駄になることはありませんので安心してください。
年末調整には関係するの?
会社員の場合、毎年11月頃に「年末調整」の用紙を会社に提出していますよね。
ふるさと納税は税金の控除が関係するため、年末調整で何か書類を添付する必要があるのではないか、と考える方もいらっしゃると思います。
結論から言うと、ふるさと納税をしても年末調整には関係ありません。
その年の収入が確定していない状態で手続きをする年末調整では、12月31日までが期限となるふるさと納税の控除手続きができないからです。
年末調整には関わりませんが、ふるさと納税では年明けに期限が設定されている控除手続きを別途行う必要があります。
手続き方法については、この後の項目で解説していきます!
会社員のふるさと納税のやり方

この項目では、会社員の方のふるさと納税のやり方を、4つのステップで詳しく説明していきます。
では、それぞれ詳しく見ていきましょう!
1.自分の控除限度額の目安を調べる
.jpg)
画像引用:総務省
ふるさと納税の第1ステップは、自分がどれくらい控除を受けられるのかの目安を調べる、ということ。
ふるさと納税は控除限度額までの寄附であれば自己負担2,000円で寄附全額が控除されるというしくみです。
控除限度額は収入や家族構成によって人それぞれ異なりますが、限度額を超えて寄附した場合、控除されるのは限度額までで、超えた分はすべて自己負担に上乗せされる形になります。
自己負担2,000円で寄附できたほうがお得ですので、まずはじめに控除限度額の目安を確認するようにしましょう!
控除額の目安は総務省の一覧表などで確認できますが、簡単に控除額がわかるシミュレーターの活用をおすすめします。
控除限度額の計算には、マイナビふるさと納税の控除額シミュレーションが便利です。
年収と家族構成を選択するだけで、自分の寄附の限度額が計算されますので、ぜひ活用してみてください!
2.自治体を選んで寄附を申し込む
ふるさと納税は、マイナビふるさと納税をはじめ、様々なふるさと納税ポータルサイトから申し込みができます。
寄附する自治体を選ぶ基準になるのは大きく2つ。
・寄附したい自治体がある
・欲しい返礼品がある
寄附したい自治体を検索し、寄附する額に応じた返礼品を選んで申し込む。
もしくは、返礼品を検索し、欲しい返礼品から寄附する自治体を選んで申し込む。
どちらの方法でもOKですので、ふるさと納税ポータルサイトに登録して申し込みをしましょう!
寄附の支払いが完了したら、自治体から返礼品が送られてきます。
申し込んだ返礼品が届くのを楽しみにお待ちください!
3.税額控除を受けるための手続きをする
ふるさと納税は、寄附をして返礼品を受け取っても、そこで終わりではありません。
寄附による税額控除を受けるため、手続きを行う必要があるのです。
控除の手続きは2種類。
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税による税額控除の手続きを簡単に行うことができる便利な制度。
ふるさと納税した自治体に必要な書類を送るだけで手続きが完了できるので、確定申告をする必要がありません。
普段、確定申告をする必要が無い会社員の方には非常に便利な手続き方法ですよね。
会社員でも確定申告をしている方がいるかと思いますが、その場合は確定申告の際にふるさと納税の分もあわせて申告しましょう。
また、手続きによって受けられる税額控除の種類が変わります。
どちらの手続きでも、最終的に受けられる控除の合計額は同じになります。
毎年の確定申告が必要ないのであれば、手続きが簡単なワンストップをおすすめします。


税額控除の手続きにはそれぞれ期限が決められていますので、必ず期限までに完了できるように余裕を持って準備しておきましょう!
4.税額控除されているか確認する
最後に、手続きによって実際に税額控除されているのか確認をしましょう。
ワンストップを利用したのであれば、控除を受けるのは住民税。
6月頃に勤務先から渡される「住民税決定通知書」で、控除額の確認ができます。
確定申告をしているのであれば、住民税と所得税の控除になりますので、「住民税決定通知書」と「確定申告書の控え」の両方で確認します。
正しく控除されたかどうかの確認方法は、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

会社員がふるさと納税をするメリットを解説!

次は、会社員がふるさと納税をするメリットを解説していきます。
そのポイントは3つ!
では、それぞれ詳しく見ていきましょう!
簡単な手続きで寄附ができる!
まず第一に、ふるさと納税は気軽に簡単にできるということ。
「ポータルサイトで返礼品を選んで寄附をする。」
これだけで、寄附を受けた自治体は寄附金を事業に活用でき、寄附した人は税額控除と返礼品を受け取れるという、シンプルでわかりやすいしくみですね。
寄附の後の控除手続きについても、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告をする必要もありません。
税金の控除を受けるとなると確定申告をするのが一般的ですが、ふるさと納税ではそれも簡略化されており、気軽に税額控除の手続きが完了できるようになっています。
このように、税額控除の手続きも簡単な寄附の制度はそう多くありません。
ぜひふるさと納税を活用してお得に寄附してみましょう!
寄附した額が無駄にならない!
一般的に「寄附」というものは、自らの意思でお金や品物を無償で提供する行為のこと。
お金に余裕のある方が行うもの、というイメージを持っている方も多いと思います。
特定の団体に寄附をすることで控除を受けられる「寄附金控除」という制度もありますが、この控除はあくまで寄附の副産物という位置付けのもので返礼品などもありません。
ですが、ふるさと納税は「お得」に寄附ができる特別な制度。
寄附したお金の合計から自己負担の2,000円を除いた全額が、翌年の税金から控除されるしくみになっています。
たとえば、控除上限が30,000円の方が30,000円ふるさと納税した場合、翌年28,000円が税金から差し引かれる形で戻ってくる。
これはつまり「自分の税金の前払い」という形ですので、ふるさと納税で寄附したお金は無駄にならないのです!
控除上限という制限はありますが、2,000円で税金を前払いできて、さらに返礼品がもらえるというお得な制度は利用しないともったいないくらいですよね。
欲しいものがお得に手に入る!
ふるさと納税の最大のメリットが「返礼品」をもらえるということ。
自治体への寄付のお礼という形ではありますが、各ポータルサイトでは返礼品から検索して寄附を申し込むこともできるようになっています。
返礼品の取り扱いは日本各地の食べ物だけでなく、メーカーの工場がある自治体では電化製品、温泉地であれば宿泊券、他にもアクティビティの利用券など様々。
返礼品を選んでいるだけでもワクワク楽しくなってしまうラインナップです。
そして、ふるさと納税の自己負担は控除上限までであれば2,000円というのがポイント。
返礼品の調達額は寄附額の30%となっていますので、たとえば30,000円ふるさと納税をすれば、2,000円の支払いで9,000円相当の品物をもらえるということになるわけです。
一旦30,000円は支払うものの、翌年には税金の控除という形で28,000円が戻り、さらに9,000円程の品をもらえてしまうんですね。
ふるさと納税は欲しいものをお得に手に入れるチャンスですので、まずはマイナビふるさと納税で返礼品を検索してみましょう!
会社員がふるさと納税する際の注意点!

会社員がふるさと納税をする際、注意しなければならない点が3つあります。
お得にふるさと納税するために、それぞれ詳しく解説していきましょう!
控除限度額は事前に必ず把握すること!
自己負担2,000円で寄附額の全額が控除される、というのがふるさと納税の特徴。
ですが、控除される額には上限があり、その限度額は収入や家族構成によって人それぞれ異なります。
控除限度額を超えて寄附した場合、超えた分の金額は全て自己負担です。
控除の対象とならない支払いが増えることになりますので、2,000円で済ませられる控除限度額までの寄附におさめるほうがよいでしょう。
ただし、限度額を超えることが損をするということとイコールではありません。
返礼品は寄附額40,000円の30%となるため、12,000円程のものになる
自己負担は12,000円になるが、返礼品の価値も12,000円程なので、実質的に金額面で損にならない
さらに、還元率(還元率=市場価値÷寄附金額)が30%を超える返礼品もあるので、実はお得になっているものもあるかもしれません。
2,000円で済ませるか、返礼品の価値によって自己負担を増やして寄附するか、このような計算をするためにも、事前に控除限度額の把握が必要です。
自分の限度額がいくらくらいなのか、必ずふるさと納税をする前に目安を把握しておきましょう!
必ず期限までに控除の手続きをすること!
せっかくふるさと納税をしても、控除の手続きが間に合わなかったら税額控除を受けられません。
ワンストップと確定申告では、それぞれ手続きの期限が違います。
特にワンストップは年が明けてすぐに期限となりますので、年末ギリギリの申し込みは注意が必要です。
控除を受けるためにも、必ず間に合うように手続きを完了させましょう!


年収が低い場合はお得にならないこともある!
ふるさと納税は、基本的に年収が多ければ多いほど控除限度額も多くなります。.jpg)
画像引用:総務省
総務省の限度額の目安の表を見てみると、年収300万円以下の項目はメリットが見込めないといわれており記載がありません。
ですが、年収300万円以下の方でもふるさと納税はできますし、300万円以下の方全てが損をするということでもないのです。

金額的な面で見て「損」になってしまう年収はこちら。
家族構成によってだいぶ差はありますが、ここに記載の年収以上であればお得になりますので、参考にしてみてください。
マイナビふるさと納税の人気返礼品ランキングTOP5!

ここからは、マイナビふるさと納税の人気返礼品ランキングTOP5を紹介していきます。
ぜひ、ふるさと納税をする際の参考にしてくださいね!
第1位:令和5年産 お米4種食べくらべ 20kg 茨城県産

人気返礼品第1位は、茨城県境町の大人気返礼品となっている「お米4種食べくらべ 20kg」です。
コシヒカリをはじめ、あきたこまち・ひとめぼれ・ミルキークイーンなど、有名な品種8種類の中から、厳選した4種類をお届けします。
令和5年産の新米になりますので、ぜひこの機会に美味しいお米4品種の食べくらべを楽しんでみてください!
第2位:やわらか厚切り牛タン【塩仕込み】計1kg(500g×2p)

第2位は、牛タンを厚切りにして特製塩だれで味付けした「やわらか厚切り牛タン 1kg」です。
厚さ約10mmというボリュームですが、柔らかく加工してスリット(切れ目)を入れてありますので、子供から年配の方まで安心して食べられます。
噛むほどに旨味があふれ出る人気の厚切り牛タンを、ぜひご自宅でお楽しみください!
第3位:オホーツク産ホタテ玉冷大(1kg)

第3位は、北海道紋別市の大粒ホタテが1kg届く大ボリュームの返礼品。
オホーツク産のホタテは、水温の低い荒波の中でたくましく育つので、養殖のホタテと比べると旨味が凝縮されていて食感も良いと評判です。
大粒で食べ応え抜群のホタテなので、お刺身やマリネ、バター焼きやフライなど様々な料理でお楽しみください!
第4位:銀鮭 切身 約2kg / 宮城東洋 / 宮城県 気仙沼市

第4位は、宮城県気仙沼市の宮城東洋から、銀鮭の切身 約2kgの返礼品。
脂のりがよくふっくらとした身が特徴の銀鮭で、独自の製法で熟成された旨味を感じることができ、凝縮した美味しさを味わえる逸品です。
一切れずつ小分けになって冷凍されていますので、2kgという大容量ですがお好みの量だけ解凍して食べられる便利さも人気となっています。
第5位:佐賀牛入り 黒毛和牛 ハンバーグ 12個 大容量 1.8kg (150g×12個)

第5位は、1日に2万個売れる究極のハンバーグが12個入った大容量の返礼品です。
黒毛和牛だけでなく佐賀牛が入っていますので、肉汁がジューシーで段違いの旨味を感じることができる絶品ハンバーグとなっています。
便利な150gずつの小包装になっており、使う分だけ解凍して焼くだけですので、手間がかからずおいしいハンバーグが味わえると人気です!
こんな返礼品も!

最後は、人気ランキングとは別に、特徴のある返礼品を紹介していきます。
それでは、「ふるさと納税最高額」、「ふるさと納税最低額」そして「ふるさと納税限定品」の3つを見てみましょう!
ふるさと納税最高額:災害復旧建設機械5点セット 350,000,000円

ふるさと納税の最高額は、災害復旧に役立つ建設機械5点セット、寄附額 3億5千万円の返礼品です。
億を超える返礼品はいくつかありますが、高額返礼品は申し込みがあるとテレビなどのニュースに取り上げられるほど話題になります。
限度額をはるかに超えた寄附額になりますので、損得抜きで寄附をしたいという方や話題性を重視される方は、高額返礼品を検討してみてはいかがでしょうか!
おつまみにうれしい!「にしんの余市干し」

ふるさと納税の最低額は、1,000円で申し込める「おつまみにうれしい!「にしんの余市干し」」。
自己負担2,000円よりも低い寄附になりますので、これ1つを申し込んだだけでは税額控除は受けられません。
ですが、控除限度額までの調整としていくつか申し込むという方法はアリです!
2,000円で申し込める返礼品は他にもたくさんありますのでチェックしてみてくださいね。
ふるさと納税限定品:【MW-TAKAMORI OUTDOOR BRAND-】アウトドアワゴン

ふるさと納税では、一般に販売されていない「ふるさと納税限定」の品物もあります。
こちらのアウトドアワゴンは、TAKAMORI BASEが一般社団法人 高森観光推進機構とプロジェクトを組んで企画・制作した、ふるさと納税でしか手に入らない限定品。
「MW-TAKAMORI OUTDOOR BRAND-」として、他にもたくさんのふるさと納税限定キャンプ用品がラインナップされていますので、ぜひチェックしてみてください!
まとめ
会社員の方のふるさと納税のやり方やおすすめ返礼品について解説してきました。
ふるさと納税をすると、寄附額が控除上限内であれば、自己負担2,000円を支払うだけで寄附全額が翌年の税金から控除されます。
それに加えて、寄附を申し込んだ自治体の特産品など返礼品を受け取ることができる、とてもお得な制度です。
さらに、控除の手続きにワンストップ特例制度を利用すると、ふるさと納税に関わる確定申告が不要に。
普段確定申告の必要が無い会社員の方にとって、非常に便利で手軽な手続き方法が用意されています。
「寄附」や「税額控除」などと聞くと難しく考えてしまうかもしれませんが、詳しく知れば気軽に簡単にできる仕組みになっていることが分かると思います。
ふるさと納税はお得ですので、ぜひ会社員の方はふるさと納税を始めてみましょう!
今回の記事を含め、マイナビふるさと納税では様々な疑問を解決できる情報が満載です。
ふるさと納税ガイドも充実しているマイナビふるさと納税で、お得に賢くふるさと納税しましょう!