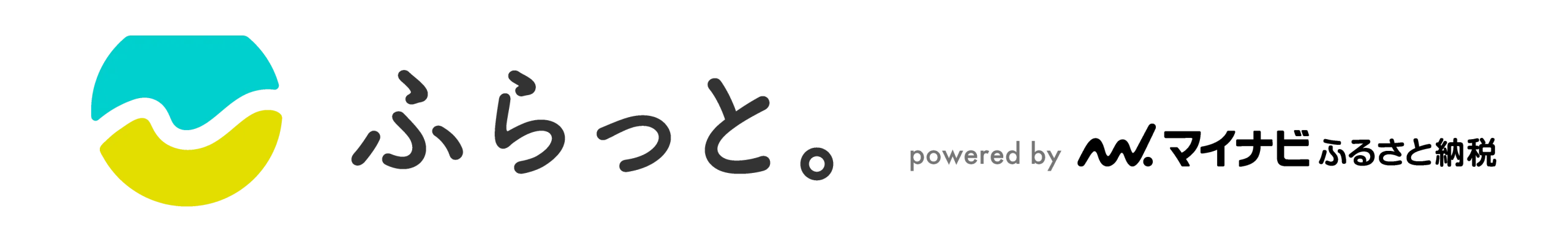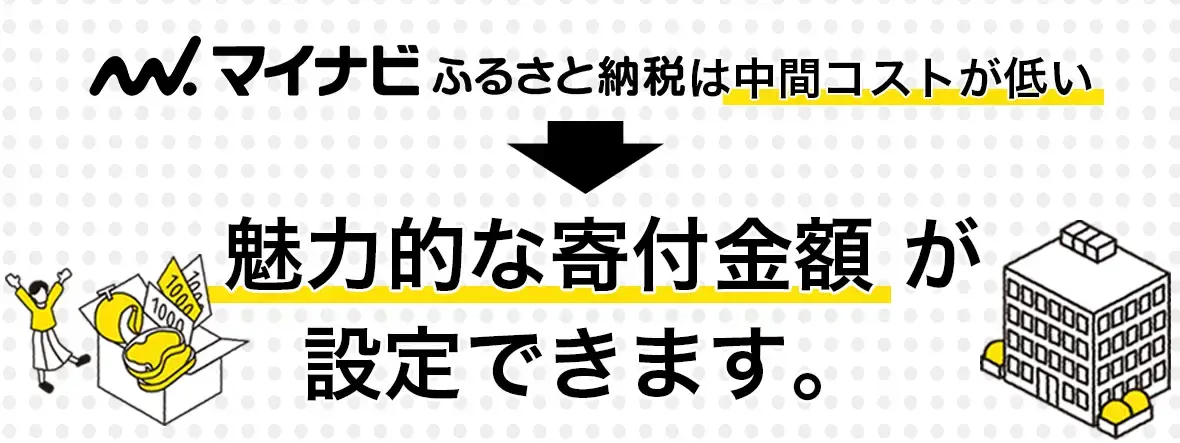誰もが大好きなフルーツの一つとしてあげられるのが「いちご」です。いちごはそのまま食べても美味しく、ケーキやジャムなどにしても美味しいですよね。
こちらの記事では、いちごの旬の時期や人気の品種、特徴、産地などを詳しく解説していきます。
いちごが美味しい旬の時期

いちごの旬は冬のイメージが強いのではないでしょうか。実はいちごの旬の時期は春頃から初夏の4月〜6月とされています。
ただ、ハウス栽培ができるようになってから、早い時期での収穫もできるようになり、11月くらいからスーパーに並ぶようになりました。
なので、正確ないちごが美味しい旬の時期は12月〜5月くらいといえるでしょう。
夏に獲れる「夏秋(かしゅう)いちご」
いちごの旬は12月〜5月といいましたが、夏にもいちごを見かけますよね。実は、6月〜11月くらいまでに収穫される「夏秋いちご」といういちごもあります。
いちごは一般的に暑さに弱く、夏の収穫は難しいとされてきていましたが、近年では冷涼な北海道や東北地方、長野県などの地域を中心に栽培されるようになってきました。
夏秋いちごの代表的な品種に「彩夏(あやか)」「サマープリンセス」「なつあかり」などがあります。
いちごの名産地TOP5!品種と特徴を解説

いちごにはたくさんの品種があり、その数はなんと約300種類以上になります。大きくて甘みがあり、ジューシーな果肉のものなど、それぞれに特徴があります。
また、日本でのいちごの名産地は生産量が多い順に栃木県、福岡県、熊本県、静岡県、長崎県です。こちらでは、いちごの名産地TOP5の主要品種を紹介します。
とちおとめ(栃木県)
とちおとめは栃木県の主要品種で、国内の生産量がもっとも多い人気のいちごです。栃木県以外にも茨城県、愛知県、など全国的に栽培されています。
果皮の色は濃い赤色で、甘味と酸味のバランスが程よいジューシーないちごです。やや大きめの果実で円錐形のものが多いです。
あまおう「福岡県」
あまおうは福岡県のオリジナルの品種で、一粒一粒のサイズが大きいのが特徴です。あまおうの名前の由来は、「あ」は赤い、「ま」は丸い、「お」は大きい、「う」はうまい、というように、あまおうの特徴の頭文字をとって名付けられました。
名前の由来通り、赤く大きく、甘みのある美味しいいちごです。一粒のサイズが大きいので、食べ応え抜群の品種です。
ゆうべに「熊本県」
ゆうべには熊本県のオリジナル品種で、「ひのしずく」と「さちのか」を交配して作られたいちごです。ゆうべにの名前の由来は、熊本県の「熊(ゆう)」といちごの赤色から「紅(べに)」をとって名付けられました。
果皮は柔らかすぎず、ツヤと光沢がある赤色です。果肉は赤と白が綺麗なグラデーションになっています。大粒で甘さと酸味のバランスがいいのが特徴です。
紅ほっぺ「静岡県」
紅ほっぺは静岡県のオリジナル品種で、「章姫」と「さちのか」を交配して作られたいちごです。紅ほっぺの名前の由来は、果皮や果肉が綺麗な赤色に染まることと、ほっぺが落ちるくらい美味しいという特徴をもとに名付けられました。
果皮はツヤがあり、果肉も中心まで赤くなります。よく熟しているものは香りもいいです。甘いのはもちろん、酸味もしっかりある、甘さと酸っぱさを楽しめるいちごです。
ゆめのか「長崎県」
ゆめのかは愛知県のオリジナル品種ですが、長崎県では主要品種の一つです。ゆめのかの名前の由来は、「みんなの夢が叶うおいしいいちご」という意味が込められて名付けられました。
果実はやや大きめで、円錐形の整った形をしています。甘味と酸味のバランスが良く、果汁がジューシーなのが特徴です。
その他いちごの人気品種4選!特徴を解説

日本国内で流通しているいちごにはまだまだ沢山の品種があります。こちらではその中でも厳選して4つの人気品種を解説します。
さがほのか
さがほのかは名前の通り、佐賀県のオリジナル品種です。果皮はツヤがあり鮮やかな赤色で、果肉は綺麗な白色です。
果肉はやや固めで甘味が強く、酸味が少ないのが特徴です。果肉がしっかりしているので、お菓子作りにも向いています。
いちごさん
いちごさんは佐賀県のオリジナル品種で、さがほのかの後継として誕生しました。2018年に品種登録され、佐賀県ではさがほのか以来20年ぶりの新品種となります。
果皮は濃い赤色で果肉まで赤くなります。果肉は甘味があり、みずみずしくてジューシーな果汁が特徴です。まだまだ新しい品種なので、世間の認知度は低いですが、収穫量も多いので人気が出ること間違いなしです。
スカイベリー
スカイベリーは栃木県のオリジナル品種です。名前の公募によって付けられた愛称で、「大きさや美しさ、美味しさが大空に届くような素晴らしいいちご」という意味が込められているそうです。
スカイベリーは大粒で形の整った円錐形で、濃い赤色です。甘味と酸味のバランスが良く、果汁も豊富でジューシーなのが特徴です。また、耐病性が強く収穫量が多いという特性も持っています。
やよいひめ
やよいひめは群馬県のオリジナル品種で、「とねほっぺ」に「とちおとめ」を交配させ、さらに「とねほっぺ」を交配させて作られたいちごです。名前の由来は、一般的に味の落ちやすい「3月(弥生)」を過ぎても品質を維持できる特性から名付けられました。
果皮は明るい赤色で、形の整った円錐形です。果肉はやや固く輸送性に優れ日持ちもします。甘味は強く酸味が少ないのが特徴です。
美味しいいちごの選び方

いちごを購入した時に「甘くない」「酸っぱい」「美味しくない」という事はありませんか?実は、美味しいいちごを選ぶのにはちょっとしたコツがあります。こちらでは美味しいいちごの選び方をご紹介します。
形が整っていてツヤのあるもの
形が均等ではなく歪ないちごは、甘さが全体にいきわたらず美味しくないものもあります。形が整っていて、ツヤのあるものの方が美味しい割合が高いです。なので、美味しいいちご選びは形とツヤに注目しましょう。
ヘタが緑色でピシッと張っているもの
ヘタが張っていなくって黒ずんでいるものは、鮮度が落ちている証拠です。なるべくヘタの色が濃い真緑でピシッと張っているものを選ぶと良いでしょう。
ヘタの周りがしっかり赤くなっているもの
ヘタの周りが白っぽくなっているものや、全体の色づきにムラがあるものは熟していなかったり、栄養が行き届いていない可能性が高いです。なるべく色のムラがなく、ヘタの周りも赤いものを選ぶのが良いでしょう。
大きめのもの
品種によって大きさは異なりますが、同じ品種で見比べた時に大きめの方が、栄養が行き届いていて美味しいことが多いです。また、大きい方が食べた時の満足度が高いといえます。なので、大きいものを選ぶと良いでしょう。
つぶつぶが隠れていて赤いもの
表面にあるいちごの種のようなつぶつぶは、いちごの果実に当たります。このつぶつぶは、埋もれていたり、表面に浮き上がっているものがあります。みずみずしいものであるほど、つぶつぶが隠れています。また、つぶつぶが赤いと熟している証拠です。つぶつぶに注目して選びましょう。
美味しいいちごの食べ方

おいしいいちごの食べ方はヘタから先端に向かって食べるのがおすすめです。何故ならいちごは、先端にいくほど甘味が増すからです。
なので、ヘタの部分から先端に向けて食べていくと、どんどん甘味が増して美味しいです。逆に先端から食べると、甘味がどんどん少なくなるので、物足りなく感じてしまう事もあります。
また、定番ですが練乳をかけて食べるのも美味しいです。ジャムにするのもパンやお菓子に使えるのでおすすめです。
美味しいいちごの保存方法

いちごは傷みやすいので、鮮度があるうちに食べる事をおすすめします。
保存をするときは、洗わずに保存しましょう。濡れた状態で放置すると傷みの原因になるので、必ずキッチンペーパーで拭き取ってから冷蔵保存しましょう。
まとめ
こちらの記事では、いちごが美味しい旬の時期と人気の品種や特徴、保存方法、食べ方などを解説しました。
昔は4月〜6月だった旬の時期も、今では冬場の方が世間的には旬といえます。また、沢山の品種があり、より美味しいいちごがどんどん開発されています。
是非、この記事を美味しいいちご選びの参考にしてみて下さい。