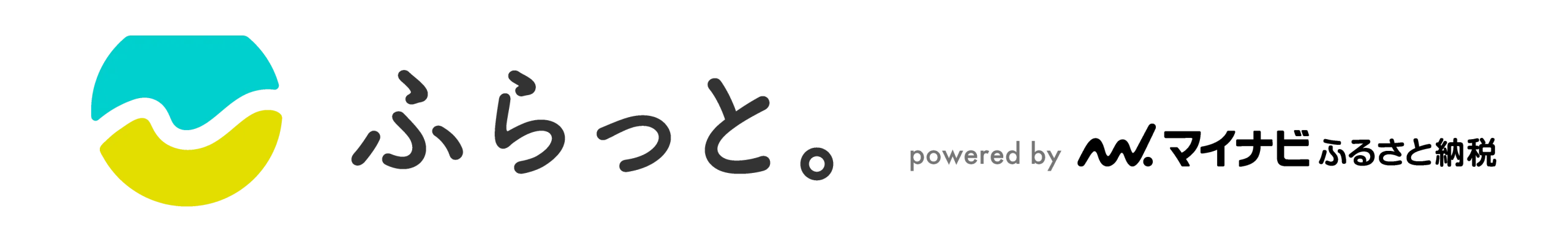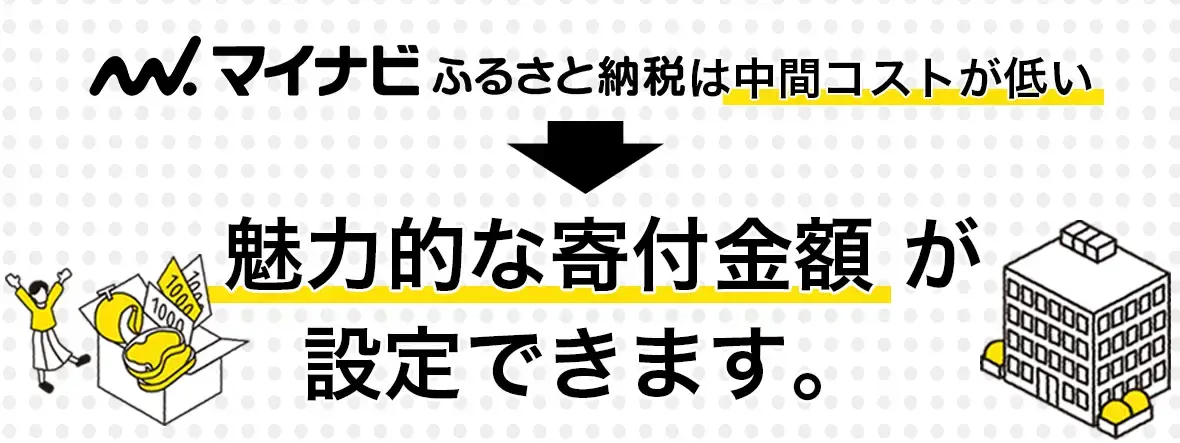「ふるさと納税はお得!」近年はそんな話題を良く耳にします。
ですが、これから始めようとしている方にとっては、分かりにくい部分もあって難しく感じてしまいますよね。
いつまでに、どのようにやったらよいのか、初心者の方は不安になって当然だと思います。
この記事では、ふるさと納税の期間について詳しく解説していきます。
知れば必ずお得にふるさと納税できるようになりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
記事の最後には、ふるさと納税のおすすめのタイミングについても解説しますのでお楽しみに!
ふるさと納税の期間はいつ?
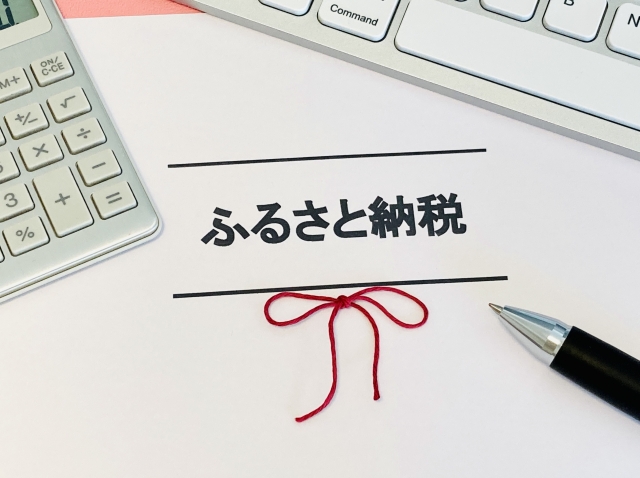
「ふるさと納税はいつまでにしなければいけないのか?」
そんな疑問をお持ちの方は結構多いのではないでしょうか。
ずばり、ふるさと納税自体に期限は決められておらず、24時間365日いつでも申し込み可能です。
ただし、翌年の税額控除を受ける手続きのため、ふるさと納税は年内いっぱいという期間で区切られており、控除の申し込みには期限が決められています。
それでは、ふるさと納税の期間について、より詳しく解説していきましょう!
ふるさと納税の期間はいつ?
ふるさと納税はいつでも申し込みできますが、それによって受けることができる税額控除の関係から、毎年1月1日から12月31日までの期間で区切られています。
・2023年の所得税が対象となり、2024年の4~5月に還付される
・2024年の住民税が対象となり、2024年の6月から控除される
このように、税額控除を受ける関係上、ふるさと納税は年内いっぱいで区切られ、翌年に還付・控除が行われるというわけです。
その年のふるさと納税として控除を受けるためには、12月31日の23時59分までに手続きが完了していなければなりません。
ふるさと納税の手続きが完了しているかどうかの確認方法は?
ふるさと納税での「手続きの完了」とは、自治体への申し込みの完了ではなく、「支払いまで完了」していることです。
寄附の支払い方法によっては手続き完了までにタイムラグが発生する場合がありますので、注意が必要です。
もし期限ギリギリでふるさと納税することになった場合、期限内に手続きが完了しているかどうか不安になってしまいますよね。
では、申し込んだふるさと納税が支払いまで完了しているかどうか、3つの確認方法を紹介していきましょう。
利用したふるさと納税ポータルサイトからの決済完了メールで確認
ふるさと納税を申し込み、手続きが完了すると、利用したポータルサイトから申し込み完了のメールが届きます。
手続きの完了が確認できますので、ポータルサイトからのメールは必ず確認するようにしましょう。
支払いが済んでいるにもかかわらずいつまでもメールが届かない場合、メールソフトによって迷惑メールとして処理されている可能性もあるので注意が必要です。
利用したふるさと納税ポータルサイトにログインして確認
ふるさと納税ポータルサイトには管理画面があり、申し込みの進捗状況などが確認できますので、ログインしてステータスを見てみましょう。
管理画面では過去の寄附履歴や、今年行ったふるさと納税の履歴も一覧で確認できます。
ふるさと納税の管理のためにも、ポータルサイトの管理画面を活用してみてくださいね。
セキュリティなどの関係で申し込み完了メールが受け取れなかった場合でも、ログインして進捗を確認することができますので安心ですね。
寄附した自治体に電話して確認
ふるさと納税で寄附した自治体の窓口に直接電話してみるという方法も。
利用したポータルサイトの自治体紹介ページには、ふるさと納税に関する問合せ窓口の案内がありますので確認してみましょう。
自治体紹介ページでは、自治体の詳細や寄附金の使い道など詳しく紹介されていますので、ふるさと納税前にも確認しておくと良いですね。
支払いが済んでしばらく経ってもステータスが完了にならないという場合、何らかのトラブルで手続きが止まっている可能性もあります。
そんなときは自治体に電話して確認してみたほうがよいこともありますので、解決の手段として頭に入れておきましょう。
期間を過ぎた場合はどうなるの?
その年のふるさと納税として翌年税額控除を受けるためには、12月31日の23時59分までにふるさと納税の手続きが完了していなければなりません。
手続きの完了が期間を過ぎてしまったものについては翌年分のふるさと納税ということになります。
2023年12月30日に申し込み、12月31日中に手続き完了 → 2023年分のふるさと納税に
2023年12月30日に申し込み、翌1月5日に手続き完了 → 2024年分のふるさと納税に
実際のところ、手続きが年を越えてしまったとしても、結果的に税額控除については無駄になることはありません。
ですが、やはりその年の分はその年の中で処理してしまうことをおすすめします。
年末に申し込みながら翌年に持ち越しになったものは、翌年分のふるさと納税として自己負担の2,000円が発生することに。
毎年継続してふるさと納税することが前提なのであれば問題ありませんが、持ち越した分で翌年のふるさと納税がスタートしていることを認識する必要があるのです。
年間の控除上限額を超えないためにも、その後の控除手続きを行う上でも、申し込んだ分は年内で手続き完了できているほうが分かりやすくて良いでしょう。
年末は魅力的な返礼品がたくさんあり悩んでしまうかと思いますが、できるだけ余裕をもってふるさと納税を行うのがおすすめ。
特に、12月は駆け込みでの申し込みが多くなり、自治体が年内の受付を早めに締めきってしまう場合もありますので注意が必要です!
ふるさと納税の税額控除の申し込み期限はいつ?

ふるさと納税は、自治体に寄付して返礼品をもらったら終了、というわけではありません。
その年にふるさと納税した分で税額控除を受けるため、年が明けたら税額控除の申し込みをする必要があります。
申し込みの種類は2つ、それぞれの期限はこちらです。
ワンストップ特例制度でも確定申告でも、最終的に控除される合計は同じ額になりますので、自分に合った方法で申し込みするようにしましょう。
それでは、2種類の申し込み方法について解説していきます。
ワンストップ特例制度の申し込み期限
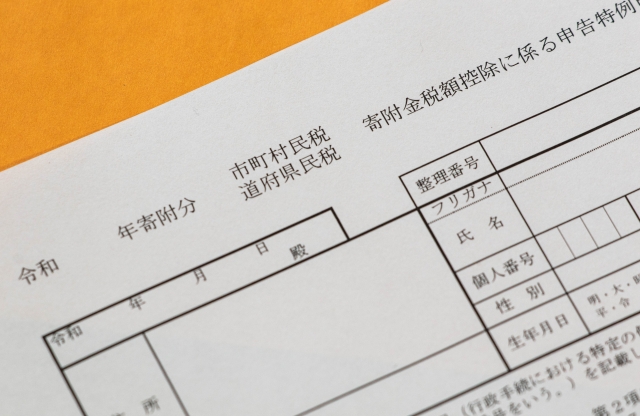
確定申告の必要がなく、手軽にふるさと納税できる「ワンストップ特例制度」。
もともと確定申告を行う必要が無いサラリーマンの方に特におすすめの申請方法です。
ワンストップ特例制度での申し込みは3つのステップ!
・申請書類に必要事項を記入
・寄附した自治体宛てに種類を郵送(1月10日必着)
自治体への書類の郵送は1月10日必着となっています。
年末に申し込みをした場合は意外と日数が少ないので、年末年始のお休みを考慮して早めに郵送するようにしましょう。
ワンストップ特例制度についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

確定申告の申し込み期限

毎年確定申告をされている方は、ふるさと納税分を合わせて申告をしましょう。
サラリーマンの方の場合、会社が所得税の納税手続きを行っていますので、通常は確定申告の必要がありません。
ですが、給与所得が多い方や副業をされている方などは確定申告が必要になる場合も。
確定申告が必要な方は以下の通りです。
・年間の給与収入が2,000万円以上ある
・2ヶ所以上の会社から給与を受け取っている
・不動産、有価証券、会員権などの売却益や譲渡益がある
・給与所得は1つの会社からあるが、その給与以外の副収入が20万円以上ある
・一定額の給与所得が2つ以上の会社からある
・住宅ローン控除(初年度)・医療費控除などの税金控除・還付を受ける
・年間の寄付先の自治体数が6つ以上ある
・ワンストップ特例制度の申し込みに間に合わなかった
ふるさと納税については、年間の寄付先の自治体数が6つ以上ある方や、ワンストップ特例制度の申し込みに間に合わなかった方も確定申告の対象になります。
普段は確定申告の必要が無くても、上記条件にあてはまれば確定申告を行わなければなりませんので注意が必要です。
確定申告の期限は2月16日~3月15日の間。
必要書類を準備し、「自宅」「税務署」「申告会場」のいずれかで行います。
ふるさと納税の確定申告についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

また、オンラインで手続きができる「e-Tax」は、自宅で簡単に確定申告ができて便利です。
ネットに接続できるパソコンやICカードリーダーライタなど、必要な環境を整えて活用しましょう!
e-Taxを利用した確定申告についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
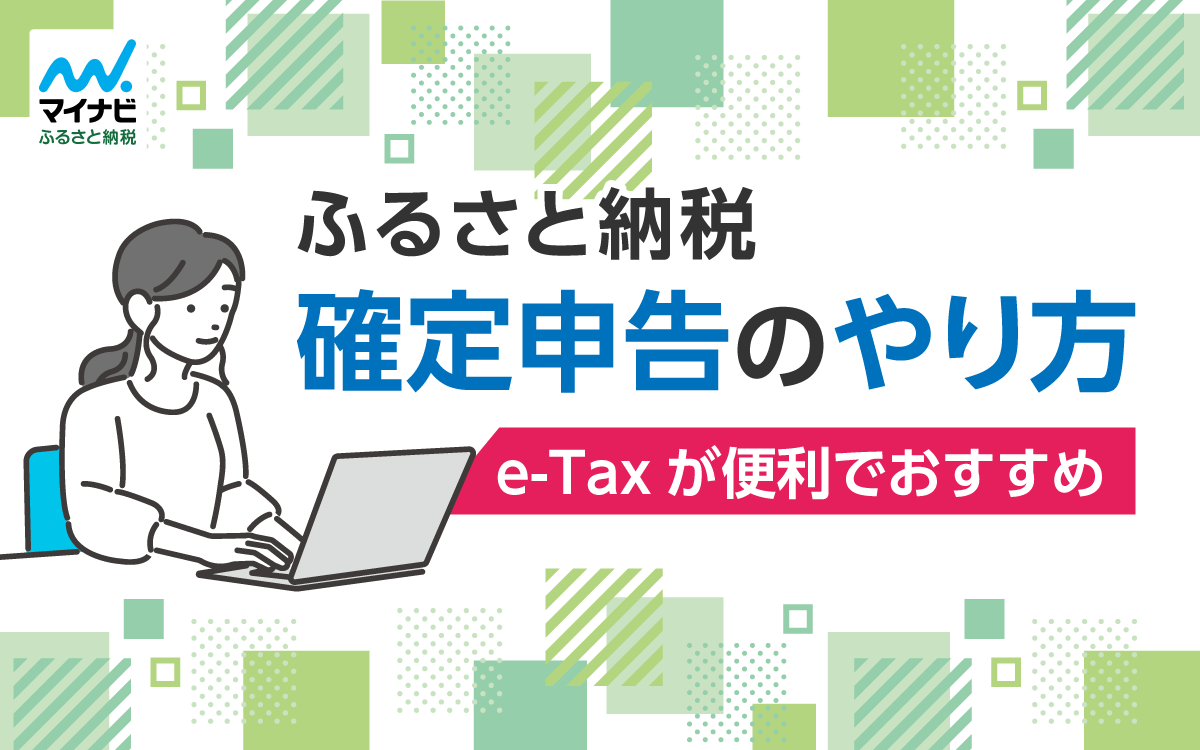
もし確定申告が間に合わなかったとしても、還付申告によって5年以内であればさかのぼって申告が可能です。
還付申告は1月1日から5年後の12月31日までが期限となっており、申告方法は確定申告とほぼ同じです。
期限は5年と長く設定されていますが、やはり分かりやすく処理するためにも、できる限りその年の分はその年のうちに申告を済ませてしまうようにしましょう。
ふるさと納税が正しく控除されたか確認する方法は?
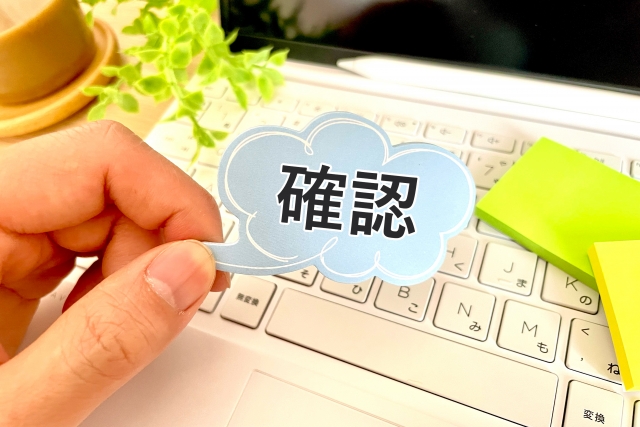
ふるさと納税をして控除の申し込みが済んだら、やはり気になるのは「正しく控除されたか」ということですよね。
ワンストップと確定申告、それぞれについて正しく控除されたかどうか確認する方法を解説していきましょう。
ワンストップ特例制度を利用した方
ワンストップ特例制度を利用した場合、翌年の住民税が控除されます。
住民税は6月頃に送られてくる「住民税決定通知書」で確認することができます。
サラリーマンの方は会社を通じて渡されることが多いですね。
住民税決定通知書に記載されている控除額が、ふるさと納税した額から2,000円を引いた額になっていれば正しく控除されたということになります。
控除額は「市町村民税」と「都道府県民税」に分かれていますので、両方の控除額を合計して計算しましょう。
控除額は、それぞれの控除額の欄に記載されている場合と、摘要欄に詳細が記載されている場合があります。
書式によって変わってきますので、住民税決定通知書をしっかり確認してみてくださいね。
確定申告をした方
確定申告をした方は、所得税の還付と住民税控除の両方を受けますので、「確定申告書の控え」と「住民税決定通知書」の両方で確認する必要があります。
確定申告書の「寄附金控除」の欄が、ふるさと納税した額から2,000円を引いた額になっていれば、控除の申請は問題ないということ。
ただ、そこから所得税還付と住民税控除がそれぞれいくらになるのかを確認するためには計算がひつようになります。
まず、所得税の還付がいくらになるのか、以下の計算式で求めます。
(所得税率は課税される所得金額によって5%~45%の7段階に区分されます)
所得税の還付金を計算したら、後に送られてくる住民税決定通知書に記載されている控除額と合計します。
その金額が、ふるさと納税した額から2,000円引いた額になっていれば、所得税還付と住民税控除の額が正確に確認できたことになるわけです。
ふるさと納税が正しく控除されたかを確認する方法はこちらの記事でさらに詳しく解説していますので参考にしてみてください!

ふるさと納税のおすすめのタイミングは?
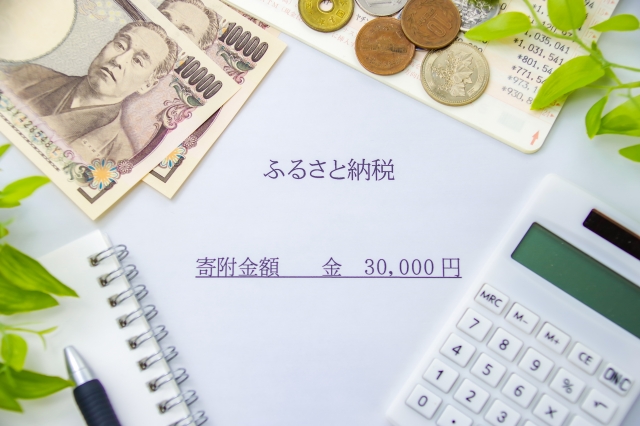
ふるさと納税は24時間365日いつでも申し込みできる、とはいえ実はおすすめのタイミングがあります。
ポイントは3つ!
それでは、ベストなタイミングでお得にふるさと納税できるよう、3つのポイントをチェックしてみましょう!
ふるさと納税が落ち着いた1月を狙う!

12月は駆け込み需要でポータルサイトの動きも重くなっており、自治体も忙しく対応が遅れることもあります。
しかし、年が明けて1月になると各所の対応も落ち着いて、手続きを含めてふるさと納税しやすくなるのです。
年末に品切れしていた人気の返礼品などが、再入荷されて申し込みしやすくなるのも特徴のひとつ。
その年のふるさと納税のスタートということで、時間に追われず余裕を持って返礼品を探せるのもメリットになるかと思います。
また、1月頃は夏に採れる果物の予約申し込みも多く見られる時期です。
話題のシャインマスカットなど人気の返礼品を狙っている方は、年明けの返礼品予約に申し込むのをおすすめします!
利用しているふるさと納税ポータルサイトのキャンペーンを狙う!

ふるさと納税の各ポータルサイトでは、時期によってキャンペーンを実施しています。
その内容は、Amazonギフト券プレゼントやPayPayポイント・楽天ポイント・ポータルサイト独自ポイントの付与など様々。
条件を満たすことで寄附額の数パーセント分が還元されるという、非常にお得なものが多いのが特徴です。
ただし、どのポータルサイトもキャンペーンは期間限定で開催されることが多いので、利用しているポータルサイトの情報は常にチェックするようにしてくださいね。
食べ物の旬の時期を狙う!

ふるさと納税でも数多く取り扱われている「食べ物」の返礼品。
食べ物にはそれぞれ美味しく食べられる旬の時期があります。
特に欲しい食材があるのであれば、旬の時期を狙って申し込みすることをおすすめします。
では、「果物の旬」「魚・甲殻類の旬」「肉の旬」について詳しく見てみましょう!
果物の旬
ふるさと納税で取り扱われている代表的な果物の旬の時期はこちら。
りんご:10月~翌2月
いちご:12月~翌2月
すいか:4月~8月
もも:6月~9月
ぶどう:8月~10月
果物は収穫のピークを過ぎると取り扱い自体が終わってしまうものもありますし、品種によっては時期がズレるものもあります。
特に人気の高い果物の返礼品を狙っている方は、旬の時期よりも早めに検索して申し込みをするようにしましょう。
魚・甲殻類の旬
魚や甲殻類の旬は、収穫の時期によって年に2回あるものも。
脂の乗った美味しい魚や、身が締まり旨味が詰まった甲殻類が食べられる旬の時期はこちらです。
ブリ:12月~翌2月
カツオ:4月~5月(初ガツオ)・8月~9月(戻りガツオ)
サンマ:9月~10月
ズワイガニ:11月~翌3月
タラバガニ:4月~6月・11月~翌2月
毛ガニ:12月~翌2月
伊勢海老:10月~翌1月
カニや伊勢海老など高級な食材もありますが、せっかくのふるさと納税ですから、少し贅沢して日本各地の絶品を食べてみるのもおすすめですよ!
肉の旬
1年を通じて取り扱われている肉類ですが、実は肉にも旬があります。
牛肉:1月~2月
鶏肉:夏以外
豚は気候が落ち着く秋頃に食欲が増えて生育が良くなるため、1年の中で肉の状態が一番良いのが秋。
牛は寒い冬を乗り越えるために脂肪を溜め込むので、1月から2月頃には抜群に脂の乗った上質な霜降りになるとのこと。
鶏肉は1年通して旬といわれていますが、夏は食欲が落ちて身が痩せるため、夏以外の時期がおすすめされているようです。
ふるさと納税では最高級の肉の取り扱いもありますので、時期を選んでさらなる贅沢をしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
ふるさと納税の期間について解説してきました。
ふるさと納税自体は24時間365日いつでも申し込み可能ですが、税額控除を受けるという性質上、1月1日から12月31日の1年間で期間を区切られています。
ふるさと納税を申し込んだ後も、税額控除を受けるための申し込みが必要です。
申し込みには期限が設定されていますので、早めに書類等を準備して忘れず手続きするようにしましょう。
また、ふるさと納税のおすすめのタイミングも紹介しました。
ポータルサイトのキャンペーンは、お得なふるさと納税がさらにお得になるものばかりですので、必ず情報をチェックして見逃さないようにしてくださいね!
ふるさと納税はその後の税額控除が関わってくるため、どうしても手続きが複雑そうに思えてしまうかもしれません。
ですが、ポイントさえおさえれば簡単にできてしまいます。
今回の記事を含め、マイナビふるさと納税では様々な疑問を解決できる情報が満載です。
ふるさと納税ガイドも充実しているマイナビふるさと納税で、お得に賢くふるさと納税しましょう!